保育園の引渡し訓練とは?

引渡し訓練の目的と必要性
毎年9月1日は「防災の日」。関東大震災を教訓に、全国的に防災意識を高める日とされています。この日に合わせて多くの保育園では「引渡し訓練」が行われています。
引渡し訓練とは、大規模な地震や災害が起きた際に、保護者が保育園に子どもを迎えに行き、安全に引き渡すまでの手順を確認・体験する訓練です。
普段は園で過ごしている子どもたちも、災害が起きたときには一変した環境に置かれます。そんな時、混乱を最小限に抑え、安全に保護者へと子どもを引き渡すための準備として、引渡し訓練は非常に重要です。
実施されるタイミングと頻度
多くの保育園では年に1〜2回、防災の日(9月1日)や防火週間、または地域の総合防災訓練に合わせて実施されます。地震や火災、洪水など、地域の特性に応じた災害を想定して訓練が行われることもあります。
災害時に想定される引渡しシーン
地震が起きた直後、電話がつながらない、道路が混雑している、保護者自身も職場から移動中……。そんな混乱の中でも、保育園は子どもたちを安全に保護者のもとへ引き渡す必要があります。
引渡し訓練では、そうした現実的な状況をできる限り再現し、「だれが・いつ・どこで・どのように」引き渡すかを確認します。非常時こそ、事前のシミュレーションが明暗を分けるのです。
防災の日に考えたい家庭との連携

家庭内で話し合っておきたいこと
引渡し訓練は保育園だけの問題ではありません。家庭でも以下のようなことをあらかじめ話し合っておくことが大切です。
-
災害時に誰が迎えに行くか(父母・祖父母・近隣者)
-
複数人が迎えに行けない場合の対応
-
お迎え時の持ち物(身分証や引渡しカードなど)
万が一、親がすぐに迎えに行けないときのために、代わりに迎えに行ける人のリストを園に提出しておくと安心です。
お迎えルート・連絡手段の確認
普段とは違うルートが必要になるかもしれません。通行止めや公共交通機関の停止を想定し、徒歩でのルートを確認しておくとよいでしょう。
また、スマートフォンのバッテリー切れや通信障害も予想されます。緊急連絡先の紙のメモを持ち歩くのもおすすめです。
災害用持ち出し袋の見直しポイント
自宅の防災リュックだけでなく、「子どもを迎えに行くための防災セット」も備えておくと安心です。
-
スニーカー(歩いて迎えに行くことを想定)
-
懐中電灯・ホイッスル
-
携帯トイレ・水・軽食
-
保育園の地図と緊急連絡先リスト
定期的に中身を見直し、使えないものや期限切れのものがないか確認しましょう。
引渡し訓練で使われるツールとは

災害用伝言ダイヤル(171)の使い方
災害時、電話回線は混雑しやすく、直接の通話が難しくなることがあります。その際に役立つのが「災害用伝言ダイヤル(171)」です。
使い方は以下の通り:
-
固定電話や公衆電話から「171」にダイヤル
-
録音(1)または再生(2)を選択
-
自宅などの電話番号を入力
-
メッセージを録音・再生
保護者同士で「171に伝言を残すルール」を決めておくと、安否確認がスムーズになります。
ちなみに私が以前勤めていた保育園では、災害用伝言ダイヤル(171)を実際に使用して、引渡し訓練を行っていました。
実施計画案が出されてから、職員同士で事前に伝言ダイヤルをかける練習をして当日を迎えていましたよ。
基本的操作方法はこちらから。↓
「災害用伝言ダイヤル(171)」の基本的操作方法 | お知らせ・報道発表 | 企業情報 | NTT東日本
安否確認アプリ・メールの活用法
最近では、保育園が導入している安否確認アプリや一斉メールシステムもあります。緊急時に園からの情報をすばやく確認できるツールとして、登録しておきましょう。
一部の園では「おたよりアプリ」や「マチコミ」などを利用しており、避難完了の情報や迎えの順番、注意事項をリアルタイムで送信しています。
園からの連絡手段の例(掲示板・一斉メールなど)
電話やアプリの他にも、園門前の掲示板や手書きメモで情報発信するケースも。
「どの手段で連絡が来るのか」を事前に知っておくことで、混乱を避けることができます。訓練時には園側の伝達手段にも注目しておきましょう。
私が勤めていた保育園ではコドモン、ルクミーの保護者一斉配信の機能を使って連絡していましたよ。
子どもを守るために保護者ができること

日常の中での防災意識の育て方
保育園では防災教育も日常的に行われています。子どもたちは「地震が来たら頭を守る」「先生の指示を聞く」といった行動を身につけています。
家庭でも、例えば「防災ごっこ」や絵本の読み聞かせなどを通じて、子どもと一緒に防災について話し合う機会をつくるとよいでしょう。
おすすめ絵本:
-
『じしんのえほん』(ポプラ社)
-
『ぼうさいダックのだいぼうけん』(こどもくらぶ)
訓練当日の持ち物と服装の注意点
引渡し訓練当日は、動きやすい服装・靴で参加しましょう。特にヒールやサンダルは避け、リュックや両手が空くスタイルがおすすめです。
また、身分証明書や引渡しカード(園で配布されることも)を忘れずに。子どもをスムーズに引き取るためには、準備も重要です。
引渡し時のスムーズな対応のために
引渡し訓練は、「保護者が迎えに来る流れ」「職員が引き渡す手順」の確認だけでなく、混乱の中でも冷静に行動するための“慣れ”を養う場でもあります。
無駄な会話は控え、決められた順序やサイン方法に従うことで、全体の流れもスムーズになります。
まとめ
引渡し訓練を「他人事」にしない意識づくり
大きな災害は、いつどこで起こるかわかりません。実際にそのときが来たとき、引渡し訓練を経験していたかどうかが子どもの安全に直結します。
「うちの地域は大丈夫」「訓練だから」と油断せず、真剣に向き合うことが大切です。
園と家庭が協力して「命を守る連携」を
引渡し訓練は、保育園と家庭、そして地域が連携して「子どもの命を守る」ための大切な訓練です。
防災の日をきっかけに、家庭でもできる備えを見直し、万が一のときに慌てずに行動できるよう、日頃から意識しておきましょう。



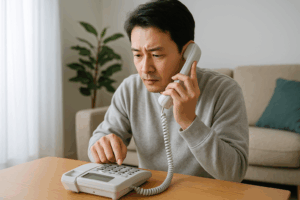









コメント