保育実習の日誌とは?基本を知ろう

なぜ日誌を書く必要があるのか
保育実習では、毎日の活動を振り返り、子どもの様子や自分の学びを整理するために日誌をつけます。日誌は単なる記録ではなく、子ども一人ひとりの姿や保育のプロセスを理解する大切なツールです。書くことで、観察力や表現力が養われ、実習後に自身の成長を客観的に確認できる貴重な資料にもなります。
また、指導保育士や実習担当者にとっても、学生の理解度や子どもへの関わり方を把握する材料になります。日誌を通して、実習先とのコミュニケーションが円滑になる点も大きなメリットです。
日誌に求められる役割と意義
保育実習日誌には大きく3つの役割があります。
-
子どもの姿を客観的に記録する
-
実習生としての気づきや学びを振り返る
-
翌日の保育につなげる材料とする
この3つを意識して書くと、単なる「作業」ではなく「学びのプロセス」として日誌を活用できるようになります。
ねらいの立て方のポイント

子どもの発達段階を意識する
ねらいを立てる際には、子どもの年齢や発達段階に合った視点を持つことが大切です。例えば、1歳児であれば「歩行が安定するように遊びの中で体を動かす機会を増やす」、3歳児であれば「友達と関わりながら協力して遊ぶ経験をする」といった具合です。漠然とした表現ではなく、発達に即した具体的なねらいを立てることで、日誌の質がぐっと上がります。
この発達段階を理解するのが実習の頃は難しかったりもしますよね。私も学生の頃の保育園実習でよく悩みました。(苦笑)
一日の活動や保育目標と結びつける
ねらいは、その日の活動内容と関連づけることがポイントです。例えば「製作活動を通して手指の巧緻性を養う」「散歩を通して自然に親しむ」といった形で、活動とねらいがセットになるように書きましょう。これにより、単なる「活動記録」ではなく「目的を持った保育」として整理できます。
保育士の視点を取り入れるコツ
学生の立場では「子どもが楽しそうだった」と書きがちですが、保育士はその裏にある発達や集団の育ちを意識しています。例えば「楽しそうだった」ではなく「友達の真似をして表現する姿が見られた」「困っている友達に声をかけていた」と具体的に書くと、保育士の視点に近づけます。
日誌の書き方と注意点

観察した事実を正確に記録する
日誌の基本は「観察の記録」です。子どもの発言や行動を正確に書き留めましょう。例えば「Aくんは絵本を見ながら『ぞうさん!』と声を出した」など、事実に基づいた記録を意識します。
一方で「Aくんは絵本が好きだと思う」といった推測は控え、根拠となる具体的なエピソードを書くことが求められます。
主観ではなく客観的に書く工夫
どうしても「楽しかった」「大変だった」といった自分の感情に偏りがちですが、日誌には客観的な事実が必要です。もちろん感想欄に感情を書いても構いませんが、観察記録と感想を区別することが重要です。
また、「〇〇してあげた」という表現も避け、子どもを主体に書くように心がけましょう。「〇〇をしていたので、一緒に取り組んだ」といった記録が望ましいです。
表現や言葉遣いで気をつけること
日誌は公式な記録です。話し言葉や省略語は避け、正しい日本語で記述しましょう。「〜でした」「〜していました」といった形で丁寧に表現するのが基本です。
さらに、子どもの名前はイニシャルで記すなど、プライバシーへの配慮も忘れないようにしましょう。
☆結構この部分は苦戦する所かもしれませんね。丁寧な日本語を使おうとするあまり二重敬語になっていたり、文章として「あれ?」となる事もあります。私は「一生懸命実習生なりに考えたんだろうな。」と思っていましたが、指導する立場になるとどうしても訂正しなければならない事もあるので、添削があったとしても次に活かそう!と前向きに捉えるといいですよ。
日誌に書く「気づき」と振り返り

子どもの反応から学べること
日誌では「気づき」を書くことが重要です。例えば「絵本を読むときに子どもたちが集中して聞いていた」「散歩の途中で虫を見つけて喜んでいた」など、子どもの反応を通して自分が学んだことを書きます。
気づきは、単なる観察記録を「学び」に変える要素です。日誌に「子どもの成長を発見する視点」を持ち込むことで、自分の理解も深まります。
自分の課題や成長に気づく視点
保育実習日誌は、自分自身の振り返りの場でもあります。「声をかけるタイミングが難しかった」「子どもの気持ちを汲み取る余裕がなかった」など、自分の課題を正直に書くことが大切です。
反対に「昨日よりも子どもに自然に関われた」「子どもの目線に合わせて話せた」など、成長した点も必ず残しましょう。実習を通して自分がどう変化しているかを実感できます。
次につながる改善ポイントを残す
振り返りでは「次はどうするか」まで考えると、学びがより深まります。「声をかける前に子どもの様子をもう少し観察する」「活動の準備物を事前に確認しておく」など、改善ポイントを明確にすることで、翌日の実習に活かせます。
☆大きな目標を掲げなくても大丈夫!自分がどんな事を明日は学びたいか、どのような事をチャレンジしてみたいかを書くと指導保育士にも伝わり、トライする機会ももらえるはずです。
まとめ|保育実習日誌は成長の記録
大切なのは「完璧さ」より「学び」
保育実習の日誌を書くとき、完璧にまとめようとするあまり時間がかかりすぎてしまう学生もいます。しかし大切なのは「きれいにまとめること」ではなく「日々の学びを記録すること」です。失敗や反省も含めて、正直に残すことが成長につながります。
日々の積み重ねが実習成功のカギ
日誌は毎日の積み重ねが大切です。最初はうまく書けなくても、続けるうちに観察力や表現力が身につきます。振り返りを積み重ねることで、実習全体を通した学びが見えてきます。
保育実習日誌は、未来の保育士としての第一歩を記す大切な記録です。焦らず、誠実に、自分なりの言葉で綴っていくことが、実習をより充実させるカギとなるでしょう。
実習日誌はその期間はとてもハードで体力的にも精神的にもきつくなることもあるかと思うけれど、保育士や幼稚園の先生になった時に「頑張ってよかった!」と必ず思えるはずなので、最後まであきらめずに乗りきってくださいね!体調管理にも気をつけて、実習期間を終えられる事を願ってます!


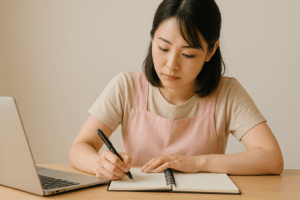
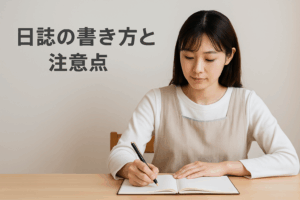









コメント