秋の夜空に美しく輝く満月。日本では古くから、9月中旬に「十五夜(じゅうごや)」として月を眺める習慣があります。保育園でも季節の行事として取り入れられることが増えており、子どもたちにとっても月や自然を身近に感じる良いきっかけとなります。
本記事では、保育園での十五夜行事の由来やアイデア、製作、絵本、保護者との関わり方まで、保育士さんに役立つ内容を幅広くご紹介します。
十五夜ってどんな日?子どもにも伝えたいお月見の意味

十五夜とお月見の由来とは
十五夜とは、旧暦の8月15日(現在の9月中旬頃)にあたる夜で、「中秋の名月」とも呼ばれます。古くから日本では、稲の実りを祝う収穫祭の一つとされてきました。
平安時代には貴族たちが月を眺めながら詩歌を詠んで楽しんだという記録もあります。その後、庶民にも広まり、ススキを飾ったり団子を供えたりして、豊作を祈る風習として定着していきました。
子どもにもわかりやすい伝え方のコツ
小さな子どもたちには、難しい言葉よりも「お月さまがきれいに見える日」「うさぎさんがぴょんぴょんしてるかもね」など、親しみやすく話してあげると理解しやすくなります。
実際に絵や写真を見せながら、「この日はお月さまにありがとうって言う日だよ」と伝えると、行事の意味にも興味をもってくれます。
「中秋の名月」ってなに?保育士が知っておきたい豆知識
「中秋の名月(ちゅうしゅうのめいげつ)」とは、秋の真ん中に見える満月を意味します。ただし、必ずしも満月になるとは限らず、1日ずれることもあります。これは旧暦と現在の暦の違いによるものです。
行事を通して「日本の文化」や「自然の不思議」をやさしく伝えることが、保育の中での大切な役割のひとつです。
保育園での十五夜行事のアイデア

お団子づくりごっこやお供え遊びで日本文化に触れる
本物のお団子を使うのが難しい場合でも、粘土で丸めた「お団子ごっこ」は人気の活動です。白い紙を丸めて作ってもOK。うさぎの耳をつけた帽子をかぶって「お月見パーティー」ごっこに発展させると、行事の楽しさが広がります。私が担任をしていた頃は紙粘土を一人ひとつ丸めてもらい、保育室内に飾っていました。お迎え時に子どもが保護者に十五夜の話をすると意外と知らない方もいて、子どもから教わっている人もいました。(笑)
また、フェルトや画用紙で作ったサトイモやススキをお供えして、「ありがとう」の気持ちを表す遊びもおすすめです。
園だよりや壁面装飾で季節を感じさせよう
玄関や保育室の壁面を、満月とうさぎ、お団子、ススキで飾りつけることで季節感が伝わります。子どもたちが作った製作を飾ると、自分の作品が行事に関わっているという実感も持てます。
また、園だよりでは「十五夜」の意味や、家庭での楽しみ方についても触れると保護者にも喜ばれます。意外と由来までは知らなかったので教えてくださりありがとうございますと伝えに来てくれた保護者の方もいたので、お便りに載せるのはおすすめです!
簡単な「お月見会」の演出や進行例
行事として「お月見会」を開く場合、以下のような流れが参考になります:
-
絵本の読み聞かせ(十五夜の絵本を使用)
-
手遊びやうた(「つき」「うさぎ」など)
-
お団子を模したお供えあそび
-
子どもたちの製作紹介や発表
-
写真撮影(うさぎ帽子や月見フォトブースで)
無理のない範囲で取り入れれば、年齢に応じて楽しい時間が過ごせます。
製作・絵本・食育で広がる十五夜の楽しみ

2〜5歳児向け!月やうさぎの簡単製作アイデア
-
2〜3歳児:シール貼りでお月さま作り。黄色い丸を貼るだけでも十分に雰囲気が出ます。
-
3〜4歳児:紙皿を使った「うさぎの耳付きお面」や「月見だんごの立体作品」など。
-
4〜5歳児:折り紙やちぎり絵でススキやうさぎを表現。絵の具で夜空を描いても素敵です。
身近な素材で楽しめる製作は、保育の導入やまとめにも使えます。
お月見にちなんだ絵本3選(読み聞かせにおすすめ)
-
『おつきさまこんばんは』(林明子)
やさしい語り口と表情豊かなお月さまに、0〜2歳児も夢中になります。 -
『うさぎの おつきみ』(きむらゆういち)
うさぎの兄妹たちが、おつきみの準備をする可愛らしいストーリー。 -
『つきよの おんがくかい』(さとうわきこ)
ババールさんのシリーズ。月夜に開かれる音楽会の幻想的な雰囲気が魅力的です。
絵本の読み聞かせをきっかけに、お月見の世界をより深く味わうことができます。
行事食・おやつで「月見団子」やさつまいもを楽しもう
給食やおやつにも「お月見要素」を取り入れると、子どもたちの記憶にも残りやすくなります。
-
月見団子風の白玉(きなこやあんこを添えて)
-
さつまいもご飯や、いももち
-
お月さま型に抜いたハンバーグや卵焼き
アレルギー対応や咀嚼力に配慮しながら、行事を感じられる工夫が大切です。
ただし、近年誤飲で喉に詰まらせてしまう事故もあるので、栄養士や調理師さんと協力するのが大事です!
保護者とのつながりを深める十五夜の工夫

おたよりや連絡帳で伝えたいこと
十五夜の活動内容や、行事の意味について簡潔に伝えると、保護者も園での学びに共感しやすくなります。
-
「今日はお月見会をしました。うさぎの製作をとても楽しんでいましたよ」
-
「お団子ごっこで“まんまる!”と嬉しそうにしていました」など、子どもの反応を交えて伝えると◎。
家庭でも楽しめる「お月見のすすめ」を共有しよう
行事を園だけで完結させず、家庭でも楽しめるように「今夜はお月見が見られそうです」「ぜひご家族で月を眺めてみてください」と一言添えると、園と家庭のつながりが深まります。
絵本の貸し出しや、簡単なお月見工作キットのプレゼントなども喜ばれる工夫です。
まとめ|保育園の十五夜行事で育む季節感と伝統文化
十五夜のお月見行事は、保育園の子どもたちにとって季節や自然、日本の伝統文化を感じる貴重な体験になります。難しく考えず、月やうさぎ、団子といった身近なモチーフから始めるだけでも十分です。
製作や絵本、行事食を通じて、楽しくやさしく「季節を感じる心」を育んでいきましょう。保護者との共有も意識しながら、行事を心あたたまるひとときにしてみてください。

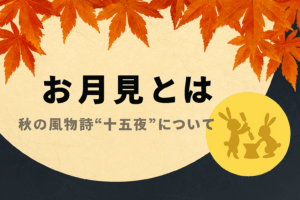











コメント