アデノウイルスとは?保育園で流行しやすい理由

どんなウイルス?(プール熱・咽頭結膜熱など)
アデノウイルスは、乳幼児の感染症の中でも特に保育園でよく見られるウイルスです。
「プール熱(咽頭結膜熱)」「流行性角結膜炎」「胃腸炎」など、さまざまな症状を引き起こすのが特徴で、同じアデノでも“型”が違うと症状が大きく異なります。
特に夏場に多いプール熱は 高熱・喉の痛み・結膜炎(目の充血) が3大症状。
冬でも感染が減るわけではなく、年間を通して発生しやすいウイルスです。
※ちなみに2025年11月現在では、インフルエンザと共にアデノウイルス感染も保育園で流行っている地域があります。
0~5歳の乳幼児がかかりやすい理由
乳幼児は免疫が未発達なため、さまざまなウイルスに感染しやすい状態です。
アデノウイルスは飛沫感染・接触感染のどちらでもうつるため、子ども同士が密に関わる場面が多い保育園では広がりやすくなります。
また、目をこする・鼻を触るなどの行動も多く、ウイルスが目や鼻から侵入しやすいことも理由のひとつです。
保育園で集団感染しやすい環境
・おもちゃやタオルの共有
・密集しやすい環境
・小さな子どもは手洗いが不十分になりがち
・アデノウイルスは環境中での生存力が非常に強い
これらが重なることで、アデノウイルスは保育園の集団生活において特に流行しやすくなります。
アデノウイルスの主な症状

高熱(39度以上が続きやすい)
アデノウイルス感染の特徴として 高熱が3〜5日続く ケースが多く見られます。
解熱剤で一時的に熱が下がっても、また上がることが一般的で、保護者は不安になりやすい場面でもあります。
喉の痛み・結膜炎(目の充血・目やに)
プール熱では、喉の赤みや痛みが強く、食欲低下・水分が飲みにくいなどの症状が出ます。
さらに結膜炎を伴うと、目の充血・大量の目やに・まぶたの腫れ が見られます。
下痢・嘔吐など胃腸症状が出ることも
アデノウイルスの型によっては、胃腸炎症状を引き起こすものもあります。
下痢が続く場合は脱水をおこしやすいため、特に注意が必要です。
症状が治まるまでの目安日数
・高熱:3〜5日
・喉の痛み:1週間ほど
・結膜炎:1〜2週間
・全体の回復:1〜2週間かかることも
症状が軽快しても、ウイルスの排出が続きしばらくうつりやすい状態が続く点も、保育園で広がりやすい理由といえます。
家庭での対処法(保護者向け)

まずは受診を|発熱・目の異変は早めに小児科へ
アデノウイルスは自宅でできる治療薬はありません。
熱が高く、喉の痛みや結膜炎がある場合は早めに小児科へ受診しましょう。
プール熱が疑われるときは医師が必要に応じて検査を行います。
水分補給と安静を最優先に
高熱が続くため、まずは 脱水予防 が最優先です。
・経口補水液
・こまめな水やお茶
・食べられるときはゼリーなど
無理に食事をさせる必要はありません。水分が取れていればOKです。
目やにのケア方法(清潔なガーゼで優しくふく)
結膜炎がある場合、目やにが増えることがあります。
・清潔なガーゼを使う
・一方向へ優しく拭き取る
・左右でガーゼを分ける
無理にこすると悪化するため注意が必要です。
家族内感染を防ぐポイント(タオルを分ける、手洗い徹底)
アデノウイルスは家庭内でも簡単に広がります。
・タオルやハンカチを共有しない
・食器を分ける
・トイレ・ドアノブなどこまめに消毒
・こまめな手洗い
兄弟がいる場合、同じ空間で遊ぶ時間を減らすなど工夫すると感染拡大を防ぎやすくなります。
兄弟がいる家庭の注意点
特に結膜炎型のアデノは感染力が強いため、兄弟が目をこすった手でおもちゃを触るだけで広がることも。
タオルや枕カバーを頻繁に洗濯するなど、環境ケアが重要です。
※ちなみに結膜炎は大人もかかるので要注意を!私も以前保育園で働いていた時にかかってしまい、大事な行事に出席する事が出来なかった事があります。
保育園での対応(保育士向け)

感染が疑われる子の観察ポイント
・38〜39度の発熱が続く
・目の充血、目やに
・喉の赤み、食欲低下
・ぐったりしている
これらが複数みられる場合は、アデノウイルスが疑われます。
クラス内での感染予防(消毒・換気・タオルの共有禁止)
アデノウイルスはアルコール消毒が効きにくいという特徴があります。
次亜塩素酸ナトリウム を使った消毒が有効です。
・おもちゃの消毒
・タオルの共有を禁止
・定期的な換気
・触れることの多い場所の拭き掃除
園全体での徹底が重要です。
目の症状が出た子のケアで気を付けること
結膜炎が見られる場合は、目やに処理のあとしっかり手洗いを行いましょう。
共用のタオルは絶対に使わないようにします。
保護者への連絡・症状説明の仕方
「熱が続く」「目が赤い」「目やにが多い」場合には即連絡を行い、早めの受診を促します。
アデノウイルスが疑われる可能性があることもお伝えすると、保護者も受診しやすくなります。
園全体での流行を防ぐためのルールづくり
・発熱時の早めの連絡
・症状のある子は無理に登園させない
・登園基準の周知徹底
これらは流行を防ぐうえで非常に重要です。
※冬場の乾燥する時期はアデノウイルスに限らず様々な感染症が広がっているので、感染症拡大を防ぐためにも早めの対応を心がけるのがベストです!そして、子ども達だけでなく先生方も移らないように気をつけてくださいね。
アデノウイルスはいつから登園できる?|登園基準

「熱が下がればOK」ではない理由
アデノウイルスは、解熱後もウイルス排出が続くため、発熱が収まったから登園できるわけではありません。
特にプール熱(咽頭結膜熱)は学校保健安全法で登校停止扱いとされており、明確な基準があります。
プール熱(咽頭結膜熱)は主要症状がすべて消えて2日経過が原則
登園できるのは
「発熱・喉の痛み・結膜炎などの主要症状がすべて治まり、さらに2日経過した後」 。
例えば症状が治ったのが月曜日であれば、水曜日以降の登園が目安です。
結膜炎症状が続く場合の登園判断
目の充血や目やにが続く場合は、登園できないことが多いです。
登園可能かどうかは医師の判断を仰ぎましょう。
医師の意見書(登園許可証)が必要なケース
園の規定によって、
・登園許可証
・医師の意見書
が求められる場合があります。保護者と連携して確認しましょう。
まとめ|アデノウイルスと上手に付き合うために
早期発見・早期受診で重症化を防ぐ
アデノウイルスは早めの受診と適切なケアで重症化を防ぐことができます。
高熱や目の異変に気づいたら、早めに医療機関へ。
園と家庭が連携して感染拡大を防ぐことが大切
保育園と家庭が情報を共有し、登園基準を守っていくことで、園全体の感染拡大を防ぐことができます。
アデノウイルスは強い感染力を持っていますが、正しい知識と対応で安心して過ごすことができます。
必要であれば、

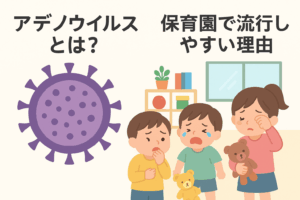



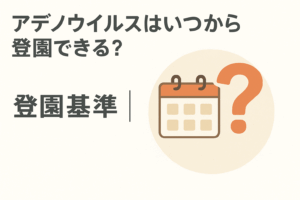








コメント