保育園で「頭がかゆい」と訴える子どもがいたとき、多くの保育士や保護者が心配するのが“アタマジラミ”です。近年は衛生環境が整っているにもかかわらず、毎年どこかの園で集団発生が報告されています。
この記事では、保育園でのアタマジラミの感染原因から治療・予防方法までを、わかりやすく解説します。
アタマジラミとは?保育園でよく発生する理由

アタマジラミの正体と感染経路
アタマジラミは、人の髪の毛に寄生して血を吸う小さな虫(寄生虫)です。大きさは約2〜3mmで、肉眼でも白っぽい小さな虫や卵(シラミの卵=“卵鞘”)が確認できます。
感染経路のほとんどは頭と頭の直接接触。ハグや肩寄せ合う遊びの中でうつるケースが多く、清潔・不潔は関係ありません。
帽子やタオル、枕などの共有によって感染することもあります。
保育園で流行しやすい時期と原因
アタマジラミは年間を通して発生しますが、特に気温が高くなる初夏から秋にかけて増加傾向です。汗をかきやすく、頭同士が触れる機会が多い季節に流行しやすいのです。
また、保育園では子どもたちが密に関わるため、一人が感染すると短期間でクラス全体に広がることがあります。
子どもが感染しやすい年齢・場面
特に多いのは、3〜6歳の幼児クラス。ブロック遊びや絵本の読み聞かせなど、頭を寄せ合う時間が長い場面で感染します。
兄弟を通じて家庭内感染が起こるケースも少なくありません。
アタマジラミの症状と見分け方

かゆみ・フケとの違いをチェック
感染すると、頭皮に強いかゆみを感じるようになります。特に耳の後ろやうなじにかゆみが出るのが特徴です。
ただし、フケと間違えることも多く、白い卵が髪にしっかりとくっついて離れない場合はアタマジラミを疑いましょう。フケは軽く払えば落ちますが、卵はしっかりついて取れません。
家庭でできる確認方法(目視・くしの使い方)
家庭での確認は、目の細かい専用くし(シラミ用コーム)を使うと便利です。髪を少し濡らし、光の下で毛束を少しずつすいていくと、動く虫や白い卵が見つかります。
卵は髪の根元から約1cmほどの位置についており、黒っぽく透けて見えるものは生きている卵の可能性が高いです。
早期発見のために保育士ができる観察ポイント
保育士は、子どもが頻繁に頭をかいたり、耳の後ろを触る様子を見逃さないようにしましょう。
お昼寝前後や整髪の際に不自然なかゆみの訴えや白い粒の付着を見つけた場合は、早めに保護者へ共有することが大切です。
アタマジラミの治療と保育園での対応

家庭での正しい駆除方法(シャンプー・くしの併用)
治療の基本は、専用のシャンプー剤を使用すること。代表的なのは「スミスリン®シャンプー」などで、薬局でも購入可能です。
使い方は、髪全体に塗布して5分ほど置き、洗い流すだけ。7〜10日後に再度使用して卵からかえったシラミを駆除するのがポイントです。
さらに、専用くしを使って卵を丁寧に取り除くことで、再発防止につながります。
園で発覚したときの対応マニュアル
保育園で感染が確認された場合は、まず個人情報に配慮しつつ保護者へ連絡を行いましょう。
その後、クラス全体に「アタマジラミが確認されました」という注意喚起文を配布し、家庭でもチェックをお願いすることが重要です。
園内では、布団や帽子、髪飾りなどの共有を一時的に控え、洗濯・天日干し・掃除機がけを徹底します。
登園はいつから可能?感染時の保護者連絡文例
アタマジラミは感染症法上の出席停止の対象ではないため、適切な治療が始まれば登園可能です。
ただし、治療開始後も卵が残っていないか確認し、保護者と連携して経過観察を行うことが望ましいです。
例文:
「お子さまにアタマジラミが確認されました。ご家庭で駆除用シャンプー等による治療をお願いいたします。治療が始まれば登園は可能ですが、再感染防止のため継続的な確認をお願いします。」
アタマジラミを予防するための工夫

家庭でできる予防対策(ヘアスタイル・共有物管理)
アタマジラミは、髪の長さや清潔さに関係なく感染しますが、髪をまとめておくことで感染リスクを減らせます。
特に女の子は、お団子や三つ編みなどで髪を束ねるスタイルが有効。
また、帽子・タオル・枕カバーなどは家族間でも共有せず、個人専用に分ける習慣をつけましょう。
園での集団感染を防ぐ取り組み例
保育園では、定期的にシーツや帽子を持ち帰らせて洗濯する日を設けると効果的です。
また、髪を乾かすときのタオルを共用しないように呼びかけるなど、日常的な小さな工夫の積み重ねが感染防止につながります。
園内での情報共有も大切で、「かゆみを訴える子が増えたら早めに確認」という体制づくりがポイントです。
子どもへの伝え方と保護者への周知のコツ
アタマジラミの話題は、子どもや保護者が「不潔」という印象を持ちやすいデリケートな内容です。
そのため、否定的な言葉を避けて前向きに伝えることが大切です。
たとえば、
「虫さんが頭の中にお出かけしてきたみたい。お薬でバイバイしようね!」
といった表現に変えると、子どもも怖がらずに治療に向き合えます。
保護者への連絡も、「流行時期に多く見られる虫の一種です」といった言葉で安心感を与えると良いでしょう。
まとめ|正しい知識と連携で安心の保育を
感染しても焦らず、冷静に対応するために
アタマジラミは、誰にでも起こりうる身近な感染症です。
早期発見・正しい駆除・家庭と園の連携によって、数日で落ち着くことがほとんどです。
大切なのは、「恥ずかしいことではない」という正しい理解を広げることです。
園・家庭・医療機関の連携がカギ
保育園では、定期的な衛生チェックや注意喚起を行い、家庭では予防意識を高めることが重要です。
場合によっては小児科や皮膚科に相談し、正しい治療を受けましょう。
アタマジラミへの対応は「誰かのせい」ではなく、園全体で支え合うことで乗り越えられるもの。
日々の小さな気づきを大切に、子どもたちが安心して過ごせる保育環境をつくっていきましょう。




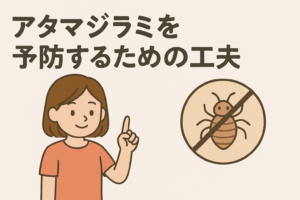








コメント