インフルエンザの流行が心配になる季節。保育園や幼稚園に通うお子さんがいると、「うちの子はもう予防接種を受けたほうがいいの?」「何歳から受けられるの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
今年はすでにもう流行し始めている地域もあるそうです。(私の友人のお子さんは幼稚園でインフルエンザにかかり、休園になっているとの事です。)
この記事では、インフルエンザ予防接種を受けられる年齢・回数・タイミングなどをわかりやすく解説します。あくまで一般的な内容をまとめていますので、実際に接種を検討する際は医師や自治体の情報も参考にしてください。
インフルエンザ予防接種は何歳から受けられる?

厚生労働省が推奨する接種開始年齢
インフルエンザワクチンは、生後6か月以降から接種が可能です。厚生労働省もこの時期からの接種を推奨しています。
0歳のうちはまだ免疫が不安定で、重症化するリスクも高いため、早めの予防接種を検討する家庭も増えています。特に、兄姉が保育園や幼稚園に通っている場合は、家庭内で感染することも多いので注意が必要です。
0歳・1歳の接種はできる?赤ちゃん期の注意点
生後6か月〜1歳未満の赤ちゃんも接種可能ですが、免疫の反応が弱く、効果が十分に出にくいこともあるといわれています。
そのため、まずは家族がしっかり予防接種を受けて、赤ちゃんを守る「家庭内バリア」を作るのがおすすめです。
1歳を過ぎたら、本人の体調をみながら小児科で相談し、初めての接種を行う家庭が多いようです。
保育園・幼稚園に通う前に接種しておくべき理由
保育園や幼稚園では、咳やくしゃみなどを通して感染が広がりやすい環境です。
インフルエンザは潜伏期間中でも感染力が高く、1人がかかるとクラス全体に広がることも。
そのため、登園を始める前の秋ごろから接種を検討しておくと安心です。園によっては「予防接種の案内プリント」が配布されることもあります。
子どもの年齢別・回数別の接種スケジュール

6か月〜2歳未満の接種スケジュール
この時期は免疫がまだ発達途中のため、2回接種が基本です。
1回目を打ってから2〜4週間あけて2回目を受けることで、十分な免疫がつくとされています。
ただし、体調を崩しやすい時期でもあるので、鼻水や発熱などがある場合は、必ず医師に相談してからスケジュールを調整しましょう。
2歳〜6歳(未就学児)の接種スケジュールとタイミング
未就学児も、基本は2回接種です。1回目から2〜4週間空けて2回目を打つのが理想です。
接種時期は、10月〜11月上旬が目安。ワクチンの効果が出るまで約2週間かかるため、12月の流行前に済ませておくのがポイントです。
園行事やクリスマスイベントなどで人との接触が増える時期でもあるので、早めに計画を立てておきましょう。
※保育園で働いていた時、12月の発表会やクリスマス会などイベント時に参加できないと辛いですよね。そのためにも上記の期間を目安に接種しておくのをおすすめします。
小学生以降の接種頻度と注意ポイント
小学生以上になると、1回接種で十分な免疫がつく場合もあります。
ただし、体質や過去の接種歴によっては2回が望ましい場合もあるため、かかりつけ医に相談しましょう。
学校行事やクラブ活動などで感染リスクが高まることを考えると、毎年1回は受けておくと安心です。
インフルエンザ予防接種の効果と副反応について

接種でどのくらい予防効果があるの?
インフルエンザワクチンは、「かからなくなる」わけではなく、重症化を防ぐ効果があります。
発症を完全に防ぐことはできませんが、熱が高くならなかったり、合併症を起こしにくくなったりといったメリットがあります。
特に小さな子どもや高齢者は重症化しやすいため、家族全員で接種しておくと安心です。
副反応の種類と家庭での対応方法
副反応としては、接種部位の腫れ・赤み・痛み、または微熱・倦怠感などが見られることがあります。
これらは通常1〜2日でおさまることが多く、特別な治療を必要としません。
高熱が続く・発疹が出るなどの強い反応が出た場合は、すぐに医療機関を受診してください。
持病やアレルギーがある場合の相談先
卵アレルギーがあるお子さんや、喘息・心疾患などの持病がある場合は、必ず事前に医師に相談しましょう。
最近は卵成分が少ないワクチンも増えていますが、医療機関によって対応が異なります。
「いつも通っている小児科」で接種を受けると、体調の変化にも気づいてもらいやすく安心です。
接種を受ける前後に気をつけたい生活の工夫

接種前に体調を整えるためのポイント
接種当日に発熱や鼻水があると、受けられないことがあります。
前日はしっかり睡眠をとり、朝ごはんを食べて体調を整えましょう。
また、午前中の早い時間帯に受けると、万が一の副反応にもすぐ対応できるのでおすすめです。
※上記には午前中に接種した方がいいと書きましたが、保育園によっては予防接種後の登園は控えてくださいという園もあります。実際に私が働いていた保育園もそうでした。理由としては接種後の登園で、小さいお子様は特に副反応が出る可能性が高いので、当日はご家庭で安静にしていてほしいという子ども第一の考えなのです。
「一日休みをとるのが難しい…」保護者の方も多いと思うので、夕方のお迎え時間を少し早めにして、夕方に予防接種するのを元保育士としてはおすすめします。
接種後の過ごし方と注意点(入浴・運動など)
接種当日は、激しい運動や長時間の入浴は控えるのが基本です。
ぬるめのシャワー程度なら問題ありませんが、体を温めすぎると腫れが悪化することもあります。
また、接種部位を強くこすらないように注意しましょう。
予防接種と併せてできる家庭での感染予防対策
ワクチンを打ったからといって油断は禁物。
家庭でもできる予防策としては、
-
手洗い・うがいをこまめに行う
-
室内の加湿と換気を心がける
-
十分な睡眠と栄養をとる
など、基本的な生活習慣の見直しが大切です。
子どもがマスクを嫌がる場合は、加湿器を活用して喉や鼻の乾燥を防ぐのも効果的です。
まとめ|家族全員でインフルエンザを予防しよう
接種のタイミングを逃さないための工夫
インフルエンザワクチンは、効果が出るまで2週間程度かかります。
流行が始まる前にしっかり免疫をつけるため、10月頃からの早めの予約がポイント。←なので、今週(10/20~)のうちに遅くても打てるとベストです!
地域や医療機関によっては予約枠がすぐに埋まることもあるので、スケジュールを確認しておきましょう。
家族で取り組む“うつさない・もらわない”生活習慣の見直し
インフルエンザの予防は、ワクチンだけでなく家庭全体の意識が大切です。
大人も子どもも、帰宅後の手洗い・うがい、咳エチケットを徹底することで感染拡大を防げます。
家族みんなで協力して、元気に冬を乗り越えましょう。

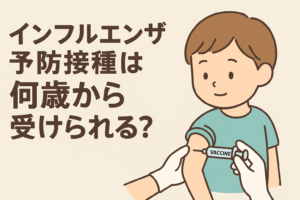
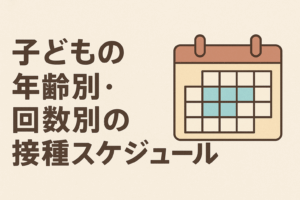
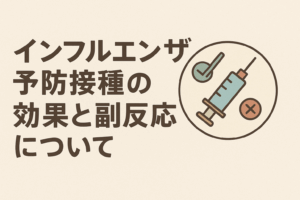
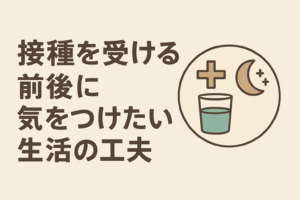








コメント