年に一度のビッグイベント「発表会」。
子どもたちが日々の成長を保護者に見てもらう大切な機会であり、保育士にとってもクラスの集大成を形にする行事です。
一方で、準備や練習に追われ、プレッシャーを感じる先生も多いのではないでしょうか。
この記事では、保育園の発表会を無理なく進めるための「ねらい」「進め方」「準備のコツ」を、年齢別の視点も交えて解説します。
保育園の発表会とは?目的とねらいを整理しよう

発表会の基本的なねらい
発表会の本来の目的は、「上手にできること」ではなく、子どもの成長過程を共有することです。
発表会を通して次のような力を育てることがねらいです。
-
自分の思いを表現する「表現力」
-
仲間と協力してやり遂げる「協調性」
-
人に見てもらう喜びによる「達成感」
また、保護者にとっても、園での姿や友だちとの関わりを見られる大切な場になります。
年齢別に異なるねらい
発表会のねらいは、年齢によって少しずつ異なります。
-
0・1歳児:保育士と一緒に楽しみながら「参加する喜び」を感じる
-
2歳児:身近な動物や食べ物などをテーマに「まねる・表現する」体験をする
-
3〜5歳児:役を理解して演じたり、曲に合わせて踊ったりすることで「達成感」や「仲間意識」を育てる
どの年齢でも、「できた・楽しかった」と感じることが一番の成長につながります。
発表会の準備スケジュールと流れ

3か月前〜テーマ決め・選曲
発表会の成功は「テーマ選び」から始まります。
クラスの興味や発達段階に合わせて、子どもたちが共感しやすい内容を選びましょう。
-
2歳児:動物や乗り物をテーマにしたかわいい表現遊び
-
3歳児:お話の世界を取り入れた劇あそび
-
4・5歳児:物語性のある劇や合奏、ダンスなど
また、曲選びは保育士のセンスが問われる部分。
近年は「ジャンボリミッキー」などの人気曲や、J-POPを子ども向けにアレンジする園も増えています。
1〜2か月前〜練習の進め方
練習が始まる時期には、まず「発表会ってどんなことをするの?」という導入を大切に。
子どもたちがワクワクしながら取り組めるよう、絵本やごっこあそびから自然に興味を広げましょう。
練習中のポイントは次の通りです。
-
短い時間で集中できるようにする(5〜10分単位)
-
「できたね!」「かっこいいね!」とポジティブな声かけを意識
-
子どもたちが自分から動けるよう、遊びの延長で導く
無理に型をはめず、「その子らしさ」を尊重することが大切です。
1週間前〜当日のリハーサルと確認
発表会前は、衣装・道具・導線の最終チェックを行いましょう。
特に大切なのは、当日の流れを職員間で共有することです。
-
入退場の順番や立ち位置を確認
-
保護者の導線・撮影ルールを明確に
-
子どもの気持ちが高まるよう「楽しみだね」と声をかける
当日は「練習の成果を見せる場」ではなく、「子どもが楽しむ日」という気持ちで臨みましょう。
発表会の内容アイデアと構成例

劇あそび
保育園の発表会で定番なのが「劇あそび」。
人気の題材は『てぶくろ』『おおきなかぶ』『三びきのこぶた』などです。
セリフを覚えることよりも、動きや表情で伝えることを重視しましょう。
保育士がナレーションを担当することで、進行がスムーズになります。
ダンス・リズム表現
身体を動かすことが好きな子どもたちには、ダンス発表もおすすめです。
知っている曲やテレビの主題歌を使うと、自然と笑顔があふれます。
-
年少:まねっこ動作の入った簡単な振り
-
年中:隊形移動や道具(リボン・ポンポン)をプラス
-
年長:フォーメーションダンスでチーム感を演出
音楽に合わせて動く楽しさを味わうことが第一です。
合奏・歌
合奏では、できる範囲で楽器を担当させ、「自分の音が加わっている」と感じさせる工夫を。
鈴・タンバリン・カスタネットなど、音の違いを楽しめる楽器がおすすめです。
歌は、季節や行事に合った明るい曲を選びましょう。
「世界中のこどもたちが」「にじ」などは、定番かつ感動を呼ぶ曲として人気です。
発表会準備の工夫とトラブル対策

子どもが嫌がる・泣いてしまうとき
発表会前になると、緊張や不安で泣いてしまう子もいます。
そんなときは無理にステージに立たせず、「見て応援する」など安心できる方法を取りましょう。
役の変更やポジション調整も柔軟に対応することで、子どもの心を守ることができます。
衣装・小道具の準備をスムーズにするコツ
衣装や小道具は、100円ショップの素材を活用するとコストも手間も抑えられます。
また、保護者協力をお願いする場合は、「どの程度までお願いするか」を明確に伝えることが大切です。
依頼文の一例:
「お子さまが安心して発表できるよう、簡単な衣装のご協力をお願いします。安全に動ける範囲でご準備ください。」
職員間の連携・役割分担
発表会はチームで作る行事です。
担任・補助・主任で役割を分けて、当日の動きを明確にしておきましょう。
-
担任:練習・進行・子どものサポート
-
補助:舞台裏の準備・衣装・小道具管理
-
主任:全体進行・保護者対応
終了後は「よかった点」「改善点」を共有し、次年度への資料として残すとスムーズです。
発表会当日の流れと保護者対応

当日のスケジュール例
-
開場・受付
-
開会あいさつ
-
各クラスの発表(年少→年長の順)
-
全園児の歌・ダンスなどフィナーレ
-
閉会・解散
撮影タイムを設定すると、保護者の混乱を防げます。
また、司会進行役が一人いると全体が締まり、安心感が生まれます。
保護者対応のポイント
保護者への案内文は、当日の持ち物・座席ルール・撮影マナーを明確に。
「頑張ったね」と声をかけたくなるような温かい雰囲気を大切にしましょう。
発表会後のフォローと振り返り

子どもたちとの振り返り
発表会が終わったら、写真や映像を見ながら「どんな気持ちだった?」と振り返ります。
「みんなに見てもらえてうれしかった」「ちょっと恥ずかしかったけど楽しかった」など、
子ども自身の言葉で気持ちを表すことが、次の自信につながります。
職員会議での振り返りポイント
-
進行のスムーズさ
-
子どもの反応
-
保護者の満足度
保護者アンケートを実施して意見を集めるのもおすすめです。
次年度の計画書や年間行事の見直しに活かしましょう。
まとめ
保育園の発表会は、子どもの「できた!」を見守る特別な日。
保育士は「指導者」ではなく、「一人ひとりを輝かせる伴走者」です。
大切なのは、上手さよりも過程を大切にすること。
準備や工夫を重ねながら、子どもも保護者も笑顔になれる発表会をつくりましょう。
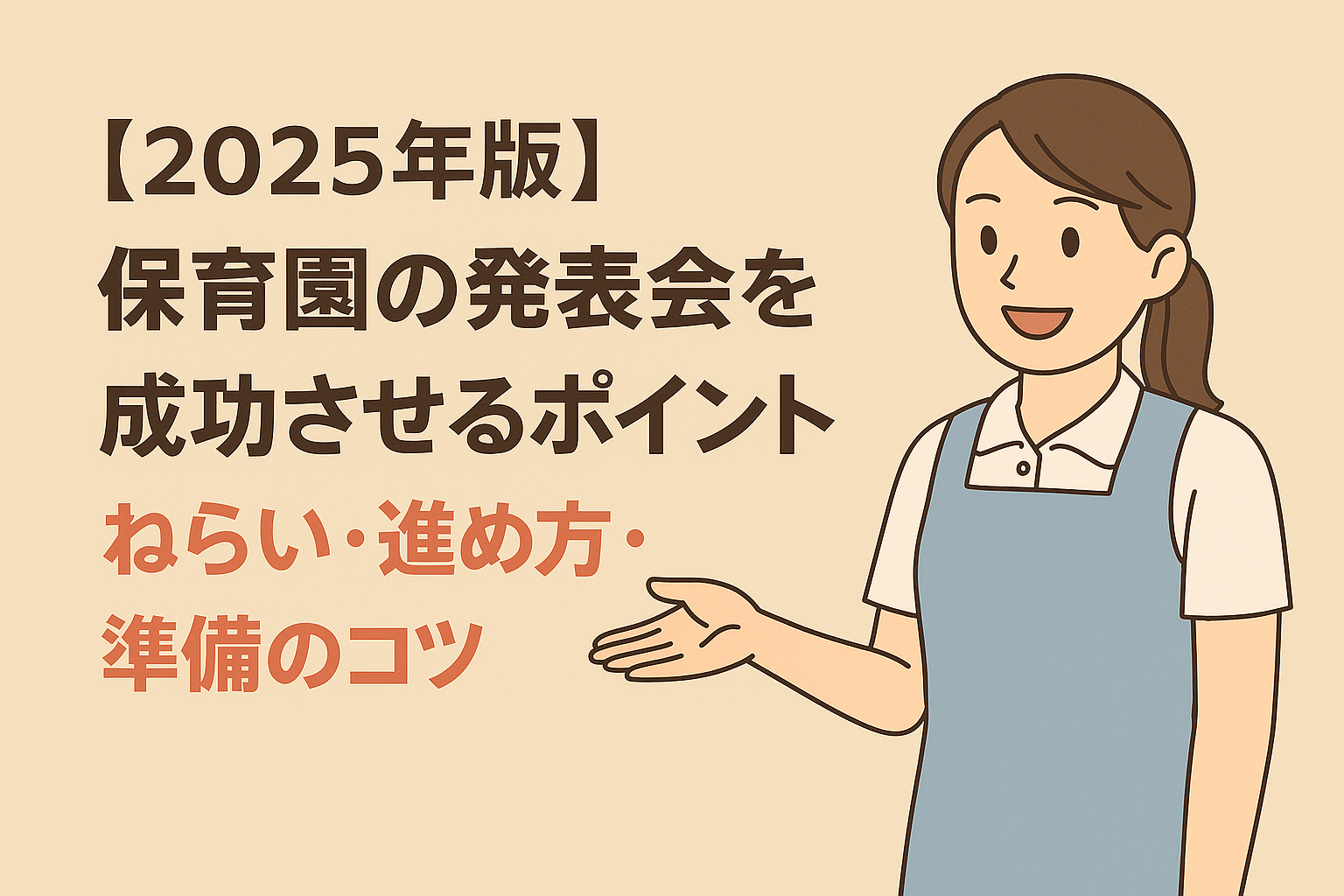

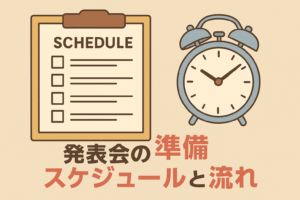
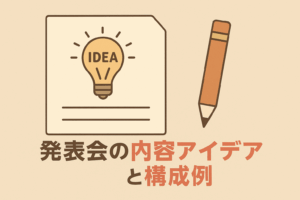
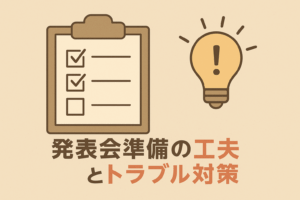
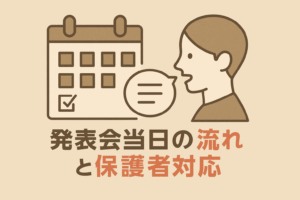
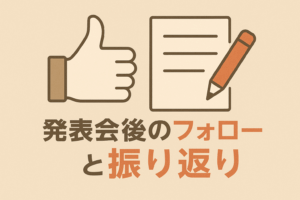








コメント