勤労感謝の日とは?子どもに伝えたい“ありがとう”の意味

どんな日?子どもにも分かる簡単な説明
11月23日は「勤労感謝の日」。
大人にとっては祝日ですが、子どもたちには少し難しい響きですよね。
保育園では、「お仕事をがんばってくれている人に“ありがとう”を伝える日」として、感謝の気持ちを育む良いきっかけになります。
「お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、先生、バスの運転手さん…」
日々の生活を支えてくれる“働く人”たちを思い浮かべながら、子どもたちの中に自然と「ありがとう」の心が芽生えます。
保育園で勤労感謝の日を取り上げるねらい
勤労感謝の日の製作活動には、次のような教育的なねらいがあります。
-
働く人への感謝の気持ちを知る
-
家族や地域とのつながりを感じる
-
自分の気持ちを“形”にして表す表現力を育む
子どもにとっては「誰かのために作る」「喜んでもらう」経験が自己肯定感を高めるきっかけにもなります。
行事を通して、“ありがとう”が自然に伝わる優しい時間をつくりたいですね。
身近な「働く人」に感謝する気持ちを育てよう
勤労感謝の日の活動は、単にプレゼントを作るだけではなく、“ありがとう”を伝える体験そのものが大切です。
「誰にあげたい?」と子どもたちに聞いてみると、思いがけない答えが返ってくることも。
お母さん・お父さんはもちろん、給食の先生や園バスの運転手さん、園長先生など、子どもが関わる身近な人を思い浮かべながら感謝の気持ちを表現できるようにしましょう。
保育園で作れる!勤労感謝の日のプレゼントアイデア10選
年齢に合わせて無理なく作れる、かわいくて気持ちが伝わる製作アイデアを紹介します。
どれも園にある材料や100円ショップの素材で簡単に作れるものばかりです。
0・1歳児向け|手形アートや写真入りカード

①手形・足形の花束カード
子どもの手形を花びらに見立てて、画用紙に貼り付けるだけ。
「ありがとう」の文字や笑顔の写真を添えれば、シンプルでも心が伝わる一枚になります。
②写真入り“ありがとうカード”
子どもの笑顔の写真を中心に、シールやクレヨンで自由にデコレーション。
0・1歳児でも指スタンプなどで参加でき、保護者にとっても成長を感じられるプレゼントです。
2・3歳児向け|花束製作や似顔絵プレゼント

③折り紙のお花ブーケ
保育士が少し手を添えながら、子どもが色を選んで花びらを貼るだけで完成。
リボンで束ねて「ありがとうカード」を添えると、本格的なプレゼントに。
④クレヨンで描く“お母さん・お父さんの似顔絵”
「どんなお顔かな?」と話しながら、思い思いの線や色で描く似顔絵。
子どもの個性が出やすく、飾ってもかわいい作品になります。
フレームを画用紙で囲むだけで、立派な“アートギフト”に。
⑤紙皿フラワーリース
紙皿の中央をくり抜き、周りに花形の画用紙を貼ってリース風に。
スタンプやシールで飾ると華やかさUP。壁掛けにもできて家庭でも飾りやすいです。
4・5歳児向け|感謝のメダル・メッセージ付きカレンダー

⑥感謝のメダル
金や銀の画用紙でメダルを作り、「いつもありがとう!」のメッセージを添えて首にかけて渡す演出が人気。
渡す瞬間に「ありがとう!」と声を合わせると、保護者の目頭が熱くなること間違いなしです。
⑦メッセージ付きカレンダー
翌年に使えるオリジナルカレンダー。
子どもが描いた絵やシールを各月に貼って、世界に一つだけの“家族カレンダー”に仕上げます。
「来年もがんばってね!」の言葉を添えると、より気持ちが伝わります。
⑧ありがとうカード+お仕事メッセージ
子どもが「お母さんは○○のおしごと」「○○してくれてありがとう」と一言書き添えるだけでも立派な作品。
言葉を通じて“働く”を身近に感じられます。
保育士も喜ばれる!子どもから先生への“ありがとう製作”

⑨園の先生に贈るメッセージカード
年長児が中心となって、先生に「ありがとう」を伝える製作もおすすめ。
園生活を支えてくれる人への感謝を実感できる時間になります。
⑩園バスの運転手さん・給食の先生へミニギフト
子どもたちが“働く人”を意識できるよう、身近な職員へのプレゼント製作も◎。
紙コップのペン立てや感謝のポスターなど、実用的で飾れる作品が人気です。
プレゼント製作の進め方とポイント

行事前の導入と子どもへの伝え方
「勤労感謝の日ってどんな日?」を子どもにも分かる言葉で伝えることから始めましょう。
「お仕事をがんばってくれている人に“ありがとう”を言う日だよ」と説明するだけでも十分です。
絵本(『ありがとうのほん』など)を取り入れると、より理解しやすくなります。
製作時のサポート方法(年齢別の援助例)
-
0・1歳児:手形・スタンプなど、感触を楽しみながら製作
-
2・3歳児:保育士が下準備をして、貼る・塗る・選ぶ工程を体験
-
4・5歳児:自分の思いを言葉や絵にして表現する段階へ
子どもの発達段階に合わせて、“できるところを任せる”ことが成功のポイントです。
渡すタイミングと伝え方の工夫
発表会やお迎え時など、家庭と自然につながる時間に渡すのがおすすめです。
「今日はお母さん・お父さんに“ありがとう”を伝える日だね」と声をかけながら渡すと、温かい雰囲気が広がります。
園全体で「ありがとうデー」としてイベント的にまとめるのも良いアイデアです。
家庭との連携アイデア|おうちでも“ありがとう”を感じよう

園で作ったプレゼントを家庭に持ち帰る際の声かけ
子どもが持ち帰る際には、保護者にも簡単なメッセージを添えましょう。
「おうちでも“ありがとう”を伝えてみてくださいね」と一言あるだけで、家庭でも行事の意味が伝わります。
家庭でもできる簡単な感謝あそび
・おうちの人に「ありがとう」を伝えるゲーム
・お手伝い体験(食器を並べる・洗濯物をたたむなど)
・“おしごとごっこ”で働くまねっこあそび
遊びの中で“働くことの大切さ”を感じられる活動を紹介するのもおすすめです。
働く家族へ「ありがとうの手紙」を伝える工夫
年長児では、家族に手紙を書くのも良い活動です。
「おしごと、いつもありがとう」「○○をしてくれてうれしい」など、短い言葉でも子どもなりの思いがこもります。
保育士が代筆してもOK。伝える気持ちを形にする経験を大切にしましょう。
まとめ|手作りプレゼントで広がる“感謝の輪”
勤労感謝の日は、子どもたちに「ありがとう」の心を育てる素敵な行事です。
保育園での手作りプレゼントは、子どもにとっても“誰かのために作る喜び”を感じられる大切な経験。
-
年齢に合わせた製作内容で無理なく楽しむ
-
“ありがとう”の気持ちを言葉と作品で表す
-
家庭とのつながりを意識して、あたたかい交流を育む
小さな作品一つひとつに、子どもたちのまっすぐな感謝の気持ちが込められています。
勤労感謝の日をきっかけに、園と家庭の間にも“ありがとう”の輪が広がるといいですね。
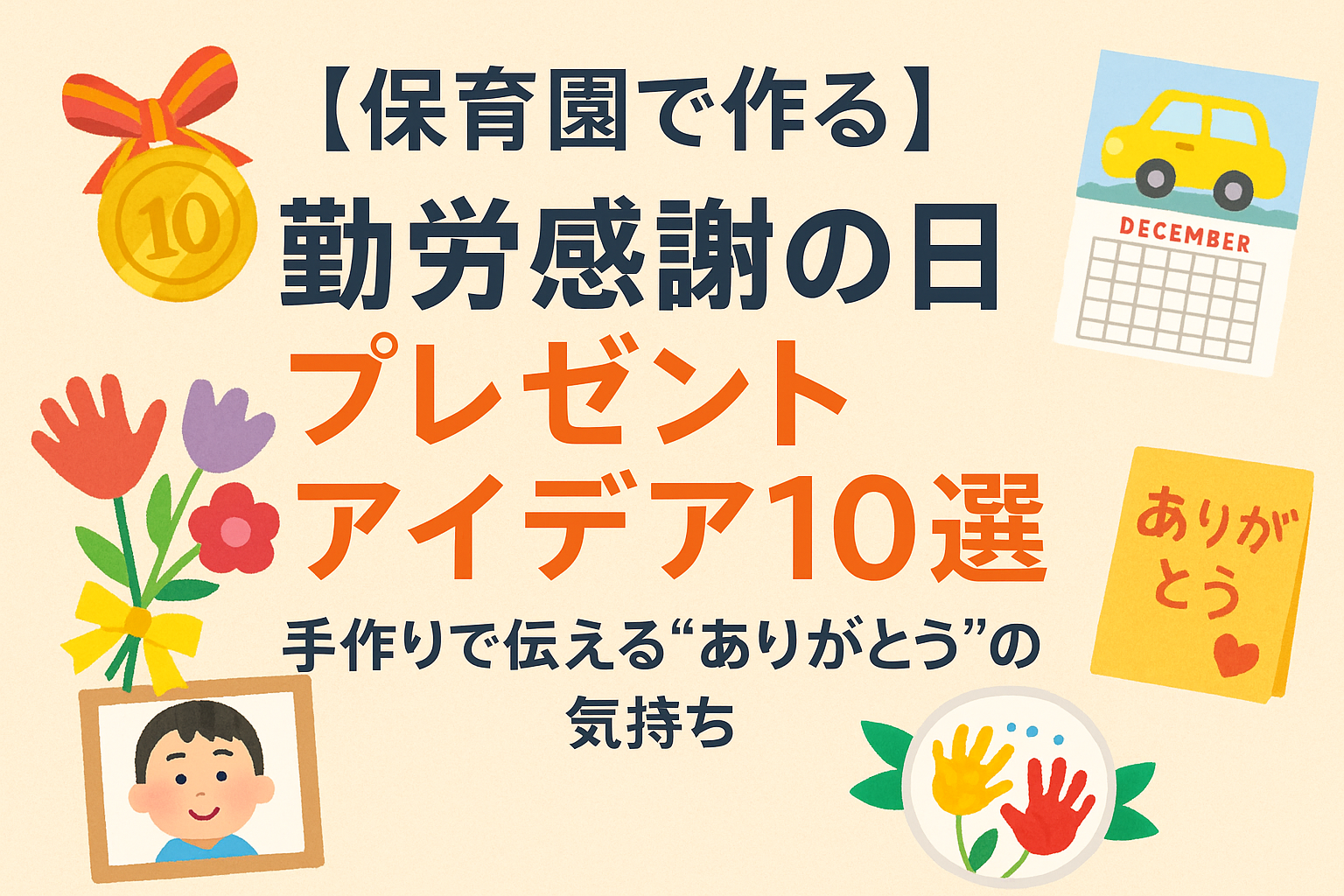















コメント