近年、子どもを中心に流行を繰り返している「マイコプラズマ肺炎」。
2025年秋も、保育園や小学校で咳が長引く症状が見られる子が増え、再び注目されています。
風邪と似ているため見分けがつきにくく、長引く咳が特徴のマイコプラズマ肺炎。
この記事では、症状・登園の目安・家庭でのケア方法をわかりやすく解説します。
マイコプラズマ肺炎とは?子どもがかかりやすい理由

マイコプラズマ菌とはどんなもの?
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマ菌(Mycoplasma pneumoniae)という微生物が原因で起こる感染症です。
細菌でもウイルスでもない「中間的な存在」で、細胞壁を持たないのが特徴。
そのため、一般的な抗生物質(ペニシリン系など)が効かず、マクロライド系抗菌薬が用いられます。
感染経路は飛沫感染と接触感染。
咳やくしゃみを通じて広がり、家族や園内での二次感染が起きやすいのが特徴です。
風邪との違い|長引く咳に注意
マイコプラズマ肺炎は「風邪」と勘違いされやすいですが、風邪よりも症状が長く続くのが特徴です。
特に咳は1〜2週間以上続くこともあり、夜になると悪化して眠れなくなるケースもあります。
熱が下がっても咳だけが残ることが多いため、「風邪が長引いている」と思っているうちに悪化してしまうことも。
※ただの風邪だろうと思っているとどんどん悪化してしまう危険性もあるので、子どもの様子を見逃さずに気づいてあげることが大切です。
5〜12歳に多いのはなぜ?
マイコプラズマ肺炎は、5〜12歳の学童期の子どもに多く見られます。
これは、免疫がまだ十分に発達していないうえに、学校や保育園での接触が多いためです。
集団生活の中では、感染が一気に広がることがあるため、園や学校での情報共有が重要になります。
マイコプラズマ肺炎の子どもの主な症状

初期症状は「発熱」と「乾いた咳」
感染初期は、発熱・のどの痛み・倦怠感といった風邪に似た症状から始まります。
しかし、次第に「コンコン」という乾いた咳が目立ち始め、徐々に強くなります。
食欲が落ちたり、声がかすれる場合もあり、体力のない子どもほど疲れやすくなる傾向です。
夜になると咳が強くなることも
マイコプラズマの咳は、夜間に悪化するケースが多いです。
寝つきが悪くなったり、咳き込みで起きてしまうこともあるため、家庭での環境づくりが大切です。
部屋を加湿し、枕を少し高くして寝かせると呼吸が楽になります。
発疹や倦怠感などの全身症状に注意
一部の子どもでは、発疹・頭痛・関節痛・下痢などの全身症状が出ることもあります。
発熱が続いたり、息苦しさ・胸の痛みを訴える場合は、肺炎を起こしている可能性があるため、早めの受診を。
マイコプラズマに子どもがかかったときの治療と家庭でのケア

抗菌薬(マクロライド系など)による治療が中心
医療機関では、マクロライド系抗菌薬(クラリスロマイシンなど)が処方されるのが一般的です。
ただし、近年はマクロライド耐性菌も報告されており、効果が乏しい場合には他の抗菌薬(テトラサイクリン系・ニューキノロン系)が選ばれることもあります。
自己判断で服薬をやめず、医師の指示に従ってきちんと飲み切ることが大切です。
無理に登園・登校させず休養を
熱が下がっても、咳が続くうちは周囲に感染を広げるおそれがあります。
「元気そうだから」とすぐ登園させるのではなく、安静に過ごす期間を確保しましょう。
体力が落ちている時期に無理をすると、治りが遅くなることもあります。
※割と多いパターンが熱が下がったから大丈夫と思い込んでしまうことです。熱は下がっても咳が出ている時は出来るだけ安静にしてあげることで治りも早くなりますよ。
家庭でできるケア|水分補給と部屋の加湿を意識
発熱や咳が続くと脱水になりやすいため、こまめな水分補給を意識しましょう。
また、部屋の乾燥は咳を悪化させるため、加湿器や濡れタオルを利用して湿度を保つのがおすすめです。
食欲がないときは無理をせず、スープやゼリーなど、のどごしの良い食事を。
家族への感染を防ぐポイント
マイコプラズマは、家庭内感染も多い病気です。
兄弟姉妹や保護者にうつさないためには、
-
咳エチケット(マスク着用)
-
タオルやコップの共有を避ける
-
手洗い・うがいの徹底
が基本です。
マイコプラズマになった子どもの登園・登校の目安

発熱が下がり、咳が軽くなってから
登園のタイミングは「熱が下がり、咳が落ち着いた頃」が目安です。
目安としては、発熱解熱後2〜3日、かつ元気が戻っていること。
医師の指示を優先することが大切
回復のスピードには個人差があるため、登園の許可は医師の診断を基準にしましょう。
医師の「登園可能」の判断を得るまでは、自宅で安静を保つのが安心です。
園・学校ごとの登園許可証の有無を確認
自治体や園によっては、登園許可証の提出を求めるケースもあります。
園便りや連絡帳などで事前に確認しておくとスムーズです。
保育園でマイコプラズマが流行したときの対応

集団生活での感染拡大を防ぐには?
園では、子ども同士の距離が近く、咳や会話を通じて感染が広がりやすい環境です。
定期的な換気、おもちゃや机の消毒、咳エチケットの指導が有効です。
発症児が出た場合は、無理をさせずに休養を促すことが大切です。
※ただし、保育園側も強制して休ませることはできないので、保護者の方に協力を促しつつ、登園した際は活動内容など配慮してあげることが大切です。
保育士が注意すべき子どもの様子
「咳が長引いている」「夜の咳で眠れずにぐったりしている」など、いつもと違う様子が見られたら早めに保護者へ共有を。
園での観察と家庭での報告を連携させることで、早期発見につながります。
家庭との連携|体調変化を共有し合う
感染症の流行期は、園だよりやアプリで「今の園の状況」を知らせると安心です。
保護者も家庭での体調変化を伝えるようにし、双方の連携で感染拡大を防ぎましょう。
☆個人が特定されないようにしつつ、園全体で共有できるようホワイトボードで掲示などする事で保護者の目にも止まりやすくなりますよ!
マイコプラズマになる前に子どもの予防法と日常でできる工夫

マスク・手洗い・咳エチケットの徹底
マイコプラズマは空気中に長時間漂うわけではないため、基本的な感染対策が有効です。
咳が出るときはマスクを着用し、帰宅後の手洗いを習慣づけましょう。
免疫力を高める生活リズムを整える
十分な睡眠・栄養・適度な運動は、感染症全般の予防につながります。
「夜更かししない」「朝ごはんを食べる」など、日常のリズムを整えることが重要です。
早期発見のために「長引く咳」を見逃さない
「もう風邪は治ったかな」と思っても、咳が2週間以上続く場合は要注意。
早めに小児科を受診し、必要に応じてレントゲン検査を受けましょう。
まとめ|マイコプラズマは早めの対応で重症化を防げる
マイコプラズマ肺炎は、子どもがかかりやすく、長引くこともある感染症ですが、
早めの受診と家庭でのケアで重症化を防ぐことができます。
保育園や学校では、咳の症状が続く子どもを見かけたら無理をさせず、
家庭と協力して安心できる回復をサポートしましょう。
咳が続く、夜に眠れない、熱が何日も下がらない——そんなときは、
「マイコプラズマかも?」と早めに気づいてあげることが、子どもの健康を守る第一歩です。


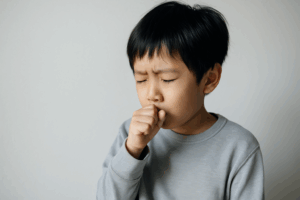

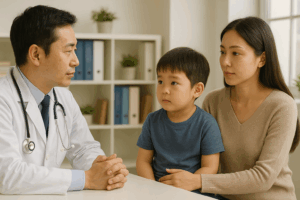










コメント