RSウイルスとは?保育園で流行する理由

RSウイルスの特徴と症状
RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)は、乳幼児の間で毎年流行する呼吸器感染症です。風邪に似た症状から始まりますが、0~2歳の子どもにとっては重症化することもあり、特に注意が必要です。主な症状は以下の通りです。
-
発熱(38度前後になることも多い)
-
鼻水や咳
-
呼吸がゼーゼーする(喘鳴)
-
ミルクや食事の摂取量が減る
大人も感染しますが、軽い風邪程度で済むケースがほとんどです。しかし、乳幼児は気道が細いため、呼吸困難に陥る可能性もあります。
特に注意が必要な年齢(0~2歳児)
RSウイルスは乳児や1~2歳児にとって、重症化のリスクが高い病気です。特に、生後6か月未満の赤ちゃんや、心臓・肺に基礎疾患を持つ子どもは入院治療が必要になることもあります。
保育園に通う子どもたちはまだ免疫が十分に発達していないため、1人が発症するとあっという間に園全体に広がってしまうのが特徴です。
※ちなみに以前私が働いていた園の0、1歳児クラスの子どもで入院してしまう子を何人も見た事があるので、意外と身近に感じてしまいます。
保育園で広がりやすい環境要因
保育園は集団生活の場であるため、咳や鼻水を介してウイルスが広がりやすくなります。
-
子ども同士の距離が近い
-
おもちゃや絵本を共有する
-
マスクの着用が難しい年齢
こうした要因から、RSウイルスは毎年保育園で大きな流行を見せるのです。
RSウイルスにかかったら保育園を何日休む?

一般的な休む期間の目安
「RSウイルス 保育園 何日休む?」と悩む保護者は多いですが、実際の休養期間は症状の経過によって変わります。
多くの場合は 発症から5~7日程度 で症状が落ち着いてきますが、咳や鼻水は長く残ることもあります。
ただし「熱が下がった=すぐに登園できる」というわけではありません。呼吸の状態が落ち着き、食欲や元気が戻るまでは家庭で休養させることが大切です。
登園許可証が必要なケース
保育園によっては「登園許可証(医師の診断書)」が必要になる場合があります。特にRSウイルスは、厚生労働省の感染症分類では「学校保健安全法に基づく出席停止の対象」ではないものの、園独自で規定を設けているケースがあります。
-
園の規則で「解熱から○日経過」などがある
-
医師の許可証を求められる
園ごとに対応が異なるため、必ず事前に確認しましょう。
☆保育園には必ず入園時に重要事項説明書などを保護者に渡していると思うので、確認してみましょう。園によって細かい部分のルールは違うので、確認しておく事が大切です。
医師の判断と園の規定の違い
医師は「もう大丈夫」と言っても、園側は「もう少し休ませてください」と判断する場合があります。これは集団生活での再感染・再流行を防ぐための措置です。
-
医師の診断=個人の健康状態を重視
-
園の判断=集団全体の安全を重視
どちらも子どもを守るための大切な視点なので、保護者は両方の意見を尊重し、無理なく登園できるタイミングを見極めることが重要です。
家庭での過ごし方とケアのポイント

休んでいる間に気をつけたい症状
RSウイルスに感染した子どもは、休んでいる間も症状が急変することがあります。以下のようなサインが見られたら、すぐに受診を検討しましょう。
-
呼吸が荒い、胸やお腹が大きくへこむ(陥没呼吸)
-
顔色が悪く、唇が紫色になる
-
水分がほとんど取れない、尿が出ない
-
ぐったりして反応が鈍い
特に乳児は重症化が早いため、少しでも不安を感じたら医療機関に相談してください。
水分補給と食事の工夫
発熱や咳で体力を消耗するため、水分補給は欠かせません。
-
水や麦茶、経口補水液をこまめに与える
-
咳き込みが強い場合は、一度にたくさんではなく少量ずつ
また、食欲がない時は無理に食べさせる必要はありません。消化の良いおかゆやうどん、果物のすりおろしなど、子どもが口にしやすいものを用意すると良いでしょう。
兄弟姉妹や家族への感染予防
RSウイルスは非常に感染力が強いため、家庭内でも広がることがあります。
-
使用したティッシュはすぐに捨てる
-
タオルや食器は共用しない
-
保護者も手洗い・うがいを徹底する
兄弟姉妹がいる場合は、別の部屋で休ませたり、接触を減らす工夫をすると二次感染を防ぎやすくなります。
登園再開の目安と保育園での対応

解熱してから何日空けるべき?
一般的には 解熱してから1~2日様子を見て 登園するのが安心です。熱が下がっても体力が戻っていなければ、再び体調を崩す可能性があります。
咳や鼻水が残っていても元気で食欲があれば登園を許可されることも多いですが、園によって基準が異なるため確認が必要です。
☆熱が下がったら一刻も早く預けたい気持ちは分かります。ただ、完全に治りきっていない状態で登園して悪化してしまうパターンもあります。
「ちゃんと治してから登園すればよかった…」なんて事にならないように体調が戻るまでは焦らないのをおすすめします。
保育園に伝えておきたいこと
登園を再開する際には、園に以下の情報をしっかり伝えると安心です。
-
医師の診断内容と登園許可の有無
-
発症から回復までの経過
-
まだ続いている症状(咳や鼻水など)
保育士が子どもの体調を把握できれば、園生活の中でも無理をさせず見守ることができます。
☆実際に担任していた時に上記の事は必ず伝えてもらっていました。+αで食事についても教えてもらえると給食やおやつの時の対応もきちんと配慮出来るので、連絡帳でも口頭でも教えてもらえると先生たちは助かりますよ!
再流行を防ぐために園ができる工夫
保育園では、RSウイルスの流行を最小限に抑えるために様々な対策をしています。
-
定期的なおもちゃや保育室の消毒
-
手洗い・うがいの習慣づけ
-
体調不良児の早めの休養対応
家庭と園が連携することで、感染拡大を防ぎ、子どもたちが安心して生活できる環境を守ることができます。
まとめ
休む日数は症状と医師の判断が基本
RSウイルスにかかった場合、保育園を休む日数は 5~7日程度が目安 ですが、最終的には医師の診断や園の規定に従うことが大切です。
家庭と保育園で協力して子どもの回復をサポート
家庭では水分補給や安静を心がけ、保育園には経過をきちんと伝えましょう。家庭と園が協力して子どもの体調を見守ることで、安心して登園を再開することができます。
「RSウイルスになったら、保育園を何日休む?」という疑問は、保護者にとって大きな不安要素ですが、症状の回復を第一に考え、無理のない登園を心がけていきましょう。

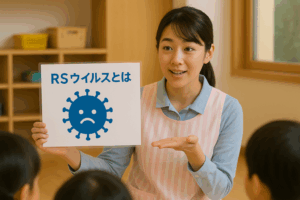











コメント