溶連菌感染症とは?保育園で流行しやすい理由

秋から冬にかけて保育園でよく耳にする「溶連菌(ようれんきん)感染症」。
子どもが突然高熱を出したり、喉が真っ赤に腫れたりして「もしかして?」と感じた経験のある保護者も多いでしょう。
溶連菌感染症は「A群溶血性レンサ球菌」という細菌による感染症で、主に喉や扁桃腺に炎症を起こします。
発症すると 発熱・喉の痛み・発疹・イチゴ舌(舌のブツブツ) などの症状が現れるのが特徴です。
感染経路と潜伏期間
感染経路は「飛沫感染」と「接触感染」。
咳やくしゃみで菌が空気中に広がったり、菌が付着した手で触ったおもちゃなどを介して広がります。
潜伏期間は1〜4日程度で、発症前から感染力があるため、保育園では一気に広がることもあります。
園で流行しやすい時期と注意点
溶連菌は一年を通して見られますが、特に 冬〜春にかけて 流行する傾向があります。
手洗い・うがいをしていても、遊びや給食、午睡などで密になりやすい保育園では感染が避けにくいのが現実。
園から「溶連菌が流行しています」というお知らせが届いたら、家庭でも子どもの体調変化に注意を払いましょう。
子どもが溶連菌に感染したらどうすればいい?

もし保育園から「お子さん、熱が高くて喉が赤いです」と連絡を受けたら、まずは落ち着いて対応しましょう。
溶連菌の多くはしっかり治療すれば数日で回復します。大切なのは 早めの受診と正しいケア です。
まずは受診!診断方法と治療の流れ
小児科では、喉の粘膜を綿棒でこすり取って「迅速検査」を行うことで、数分で溶連菌かどうかが分かります。
陽性の場合は抗生物質(ペニシリン系など)を7〜10日間処方されるのが一般的です。
「熱が下がったから」といって薬を途中でやめると、菌が体に残って再発や合併症の原因になることも。
医師の指示通り最後まできちんと服用する ことが何より大切です。
家庭でのケアのポイント
・喉の痛みが強いときは、ゼリーやスープなどの やわらかい食事 に
・高熱時は 水分補給をこまめに(麦茶・経口補水液など)
・寝具やタオルは 家族で分けて使用
・食器類もできれば別にし、よく洗う
無理に登園させるよりも、まずはしっかり休ませることが回復への近道です。
☆秋から冬にかけて保育園のイベントや行事が多くなるとは思うのですが、お子さんの体調がいまいち優れない場合は無理をさせずに休ませてあげましょう。
保育園は何日休む?登園の目安と医師の診断書について

「熱が下がったけど、いつから登園できるの?」
多くの保護者が悩むのが、登園再開のタイミングです。
登園できるのは「抗生物質を飲み始めて24時間後」が目安
一般的に、抗生物質を服用して 24時間(1日)経過 すると感染力がほぼなくなるといわれています。
そのため、医師から「もう大丈夫」と許可が出れば登園可能です。
ただし、園によっては「抗生物質を飲み始めて2日後」「熱が下がってから2日後」など、独自の基準を設けている場合もあります。
まずは 通っている園の登園基準 を確認し、担任や園長に報告・相談しましょう。
※自治体は保育園によって違うので、保育園の入園のしおりや重要事項説明書などを確認してみましょう。それでも書いていない場合は確認してみるといいですね。
医師の診断書や治癒証明は必要?
自治体や園の方針により異なりますが、登園前に 医師の「登園許可証」や「治癒証明書」 の提出を求められることがあります。
受診時に園から渡された書類があれば持参し、医師に記入してもらいましょう。
近年では「口頭確認でOK」とする園も増えていますが、感染症拡大を防ぐためにも、書面が必要な場合は速やかに提出を。
園への連絡マナー
欠席が分かった時点で早めに連絡を入れましょう。
その際、
-
溶連菌感染症と診断されたこと
-
抗生物質を飲み始めた日時
-
医師の登園許可が出たら再度報告する旨
を伝えておくと、園側もスムーズに対応できます。
登園後も気をつけたい!再感染・合併症の予防

元気になったからといって油断は禁物。
溶連菌は一度かかっても 再感染することがあります。
再感染を防ぐためにできること
・うがい・手洗いをしっかり行う
・歯ブラシは新しいものに交換
・枕カバーやシーツを洗濯して清潔に保つ
兄弟姉妹や家族にうつるケースも多いので、感染拡大を防ぐ意識を持ちましょう。
合併症のサインに注意
まれに、溶連菌感染症の後に「急性糸球体腎炎」や「リウマチ熱」などの合併症を起こすことがあります。
治療後1〜3週間ほど経ってから
-
顔や足がむくむ
-
尿の色が赤っぽい
-
関節が痛い
といった症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診してください。
園と家庭でできる予防・衛生対策
保育園では、手洗い指導やタオルの個別使用、玩具の消毒などを徹底しています。
家庭でも、
-
ハンカチ・マスクの持参
-
食事前後の手洗い習慣
-
体調が悪いときは無理せず休む
といった基本を大切に。
園と家庭が協力して予防意識を高めることで、感染の広がりを防ぐことができます。
まとめ|焦らず正しく対応して、安心して登園を迎えよう
子どもが溶連菌にかかると、仕事の調整や看病で保護者も大変ですよね。
でも、適切な治療を受け、安静に過ごせば数日で回復するケースがほとんどです。
-
早めに小児科を受診し、抗生物質をきちんと飲み切る
-
登園は医師の許可と園の基準を確認してから
-
家族内感染や再発を防ぐための衛生対策も忘れずに
これらを守れば、安心して登園再開の日を迎えられます。
子どもの健康を第一に、園と家庭が連携しながら無理のない対応を心がけましょう。



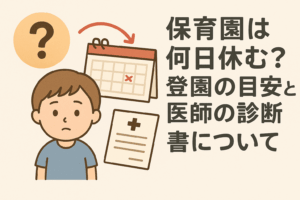









コメント